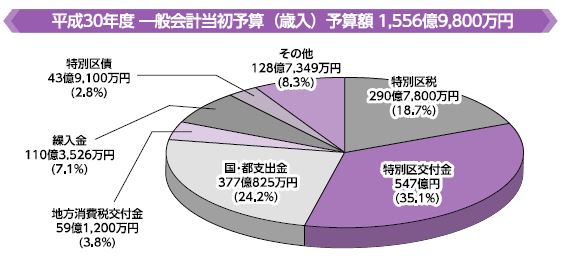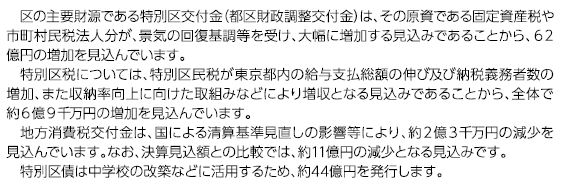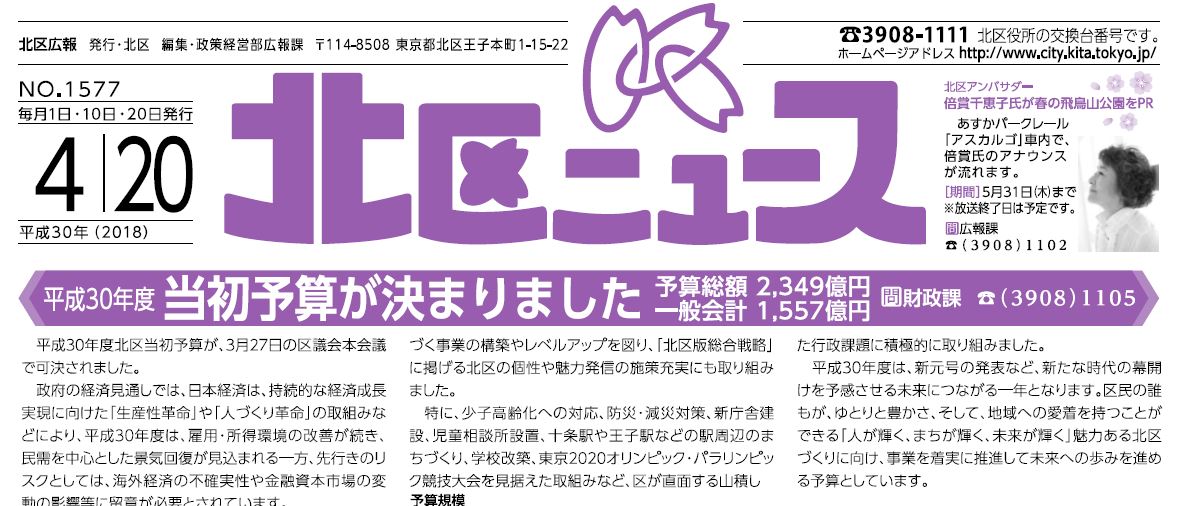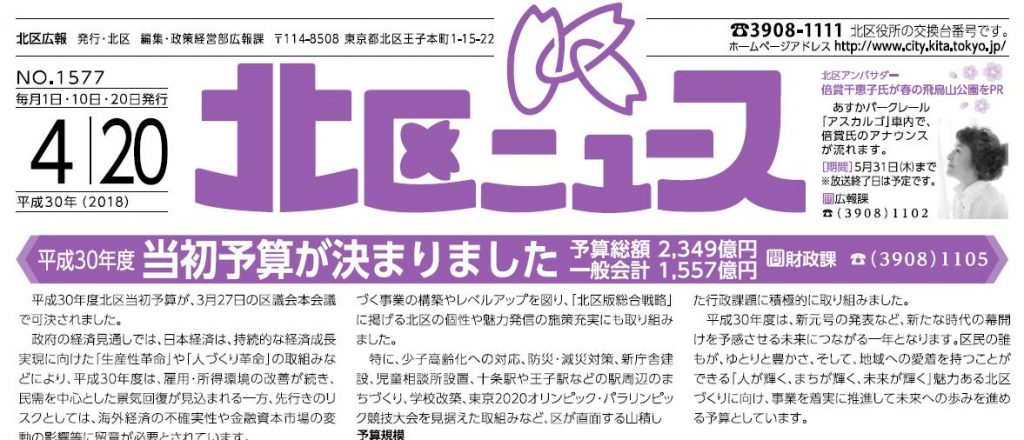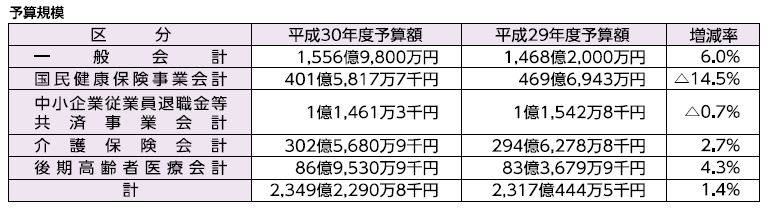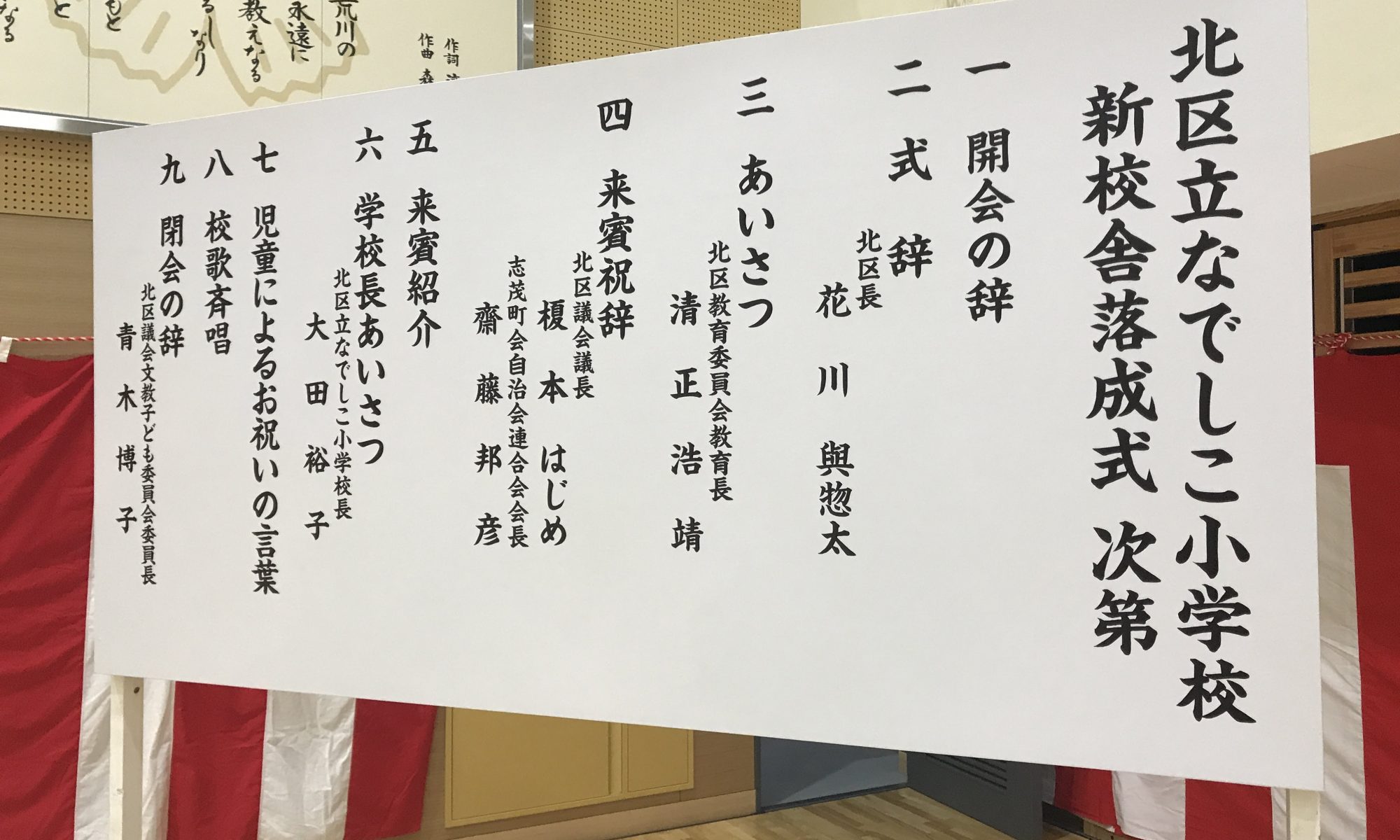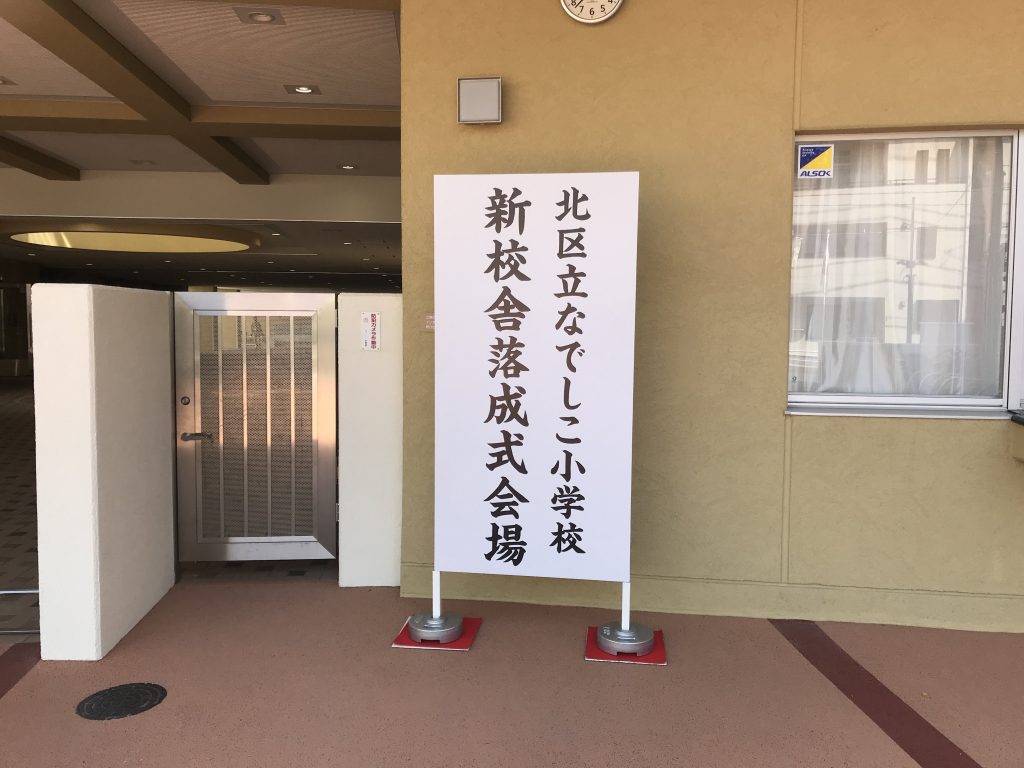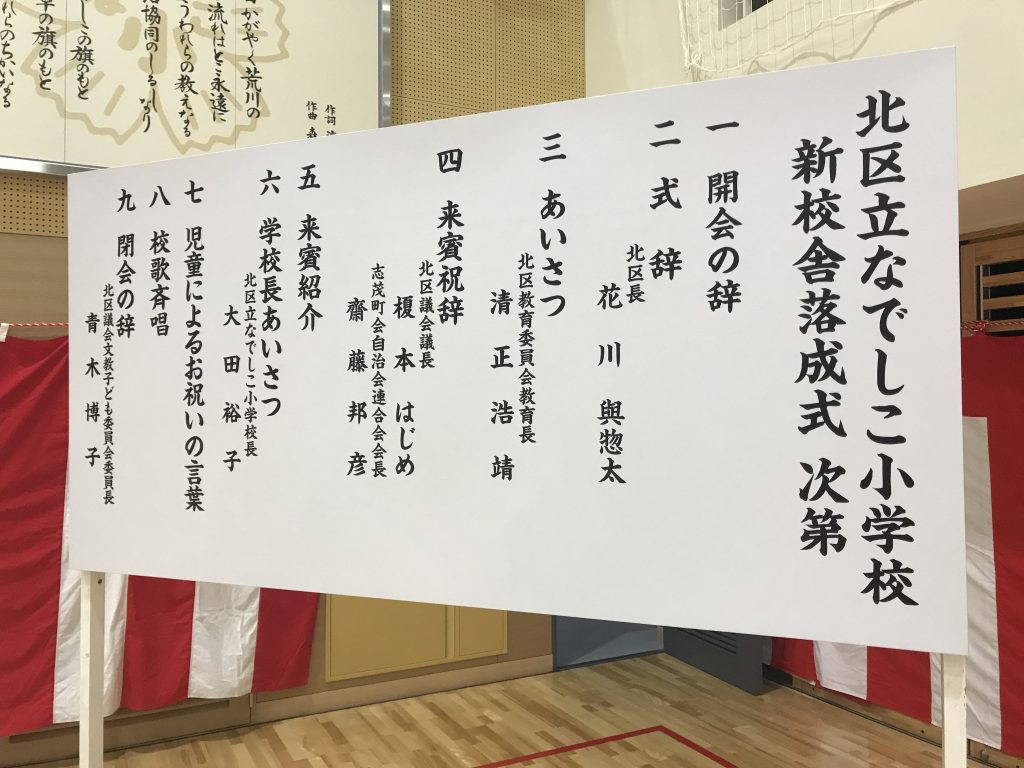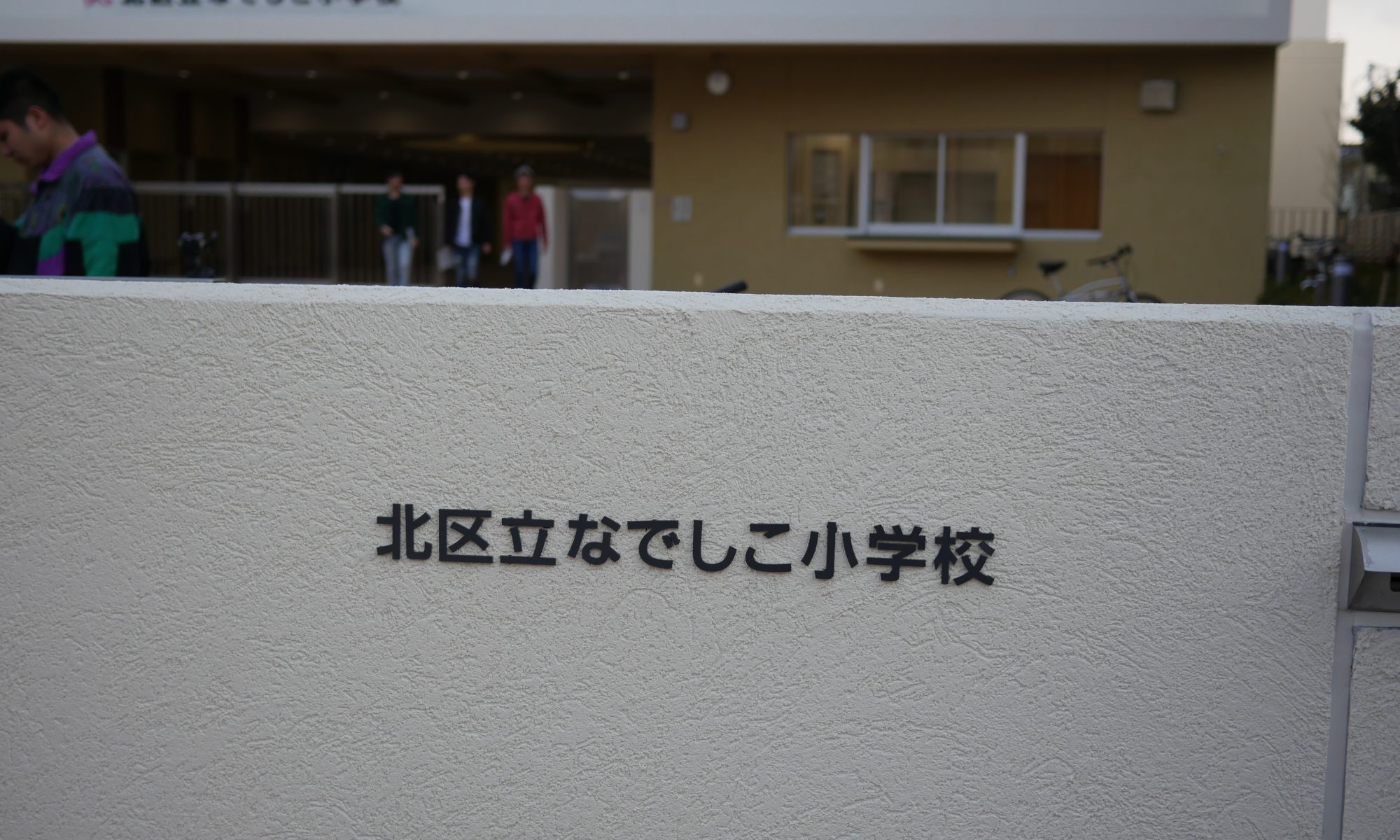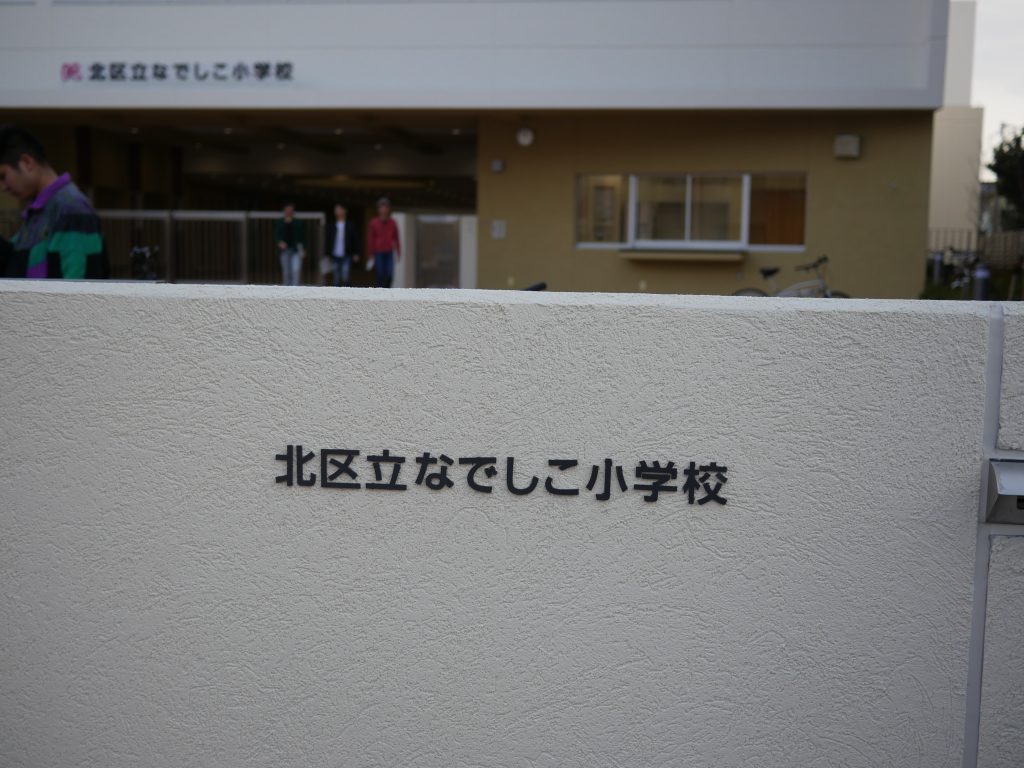おはようございます。こんにちは。こんばんは。
東京都北区のShimoです。
昨日は、毎月恒例の親しい士業仲間による定例の「赤羽会」を行いました。
「赤羽会」とは有志の飲み仲間の仮称です。
私は行政書士の資格も持っています。何かの間違いで行政書士試験に合格してしまったので、社会勉強のために行政書士登録もしてみました。
今朝午前5時の北グラウンド
すると、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士やプランナーフィナンシャルプランナーといった士業の仲間ができて、月に一度の頻度で情報交換を兼ねて食事会を継続しています。
通常は赤羽のお店を会場とすることが多いのですが、今回は初めて王子のお店に遠征に行きました。
何となく波長の合う仲間同士なので毎回非常に楽しい会になるのですが、この日も有意義な話し合いができて気分良く家に帰ってみると、うちの奥さんと娘が何やら険悪な雰囲気です。
多分、話の発端は大した事ではなかったものの、2人で話しているうちに何かヒートアップしてしまうような流れになったのだと思います。
うちの奥さんは、「娘が親の言うことを聞かない」と私に訴えます。
娘は、「喧嘩を売ってくるママが悪い」と私に訴えます。
この手の話は各家庭で様々なので、話を解決する特効薬があるとは思いませんが、うちの場合は母親である私の奥さんに、「娘に対してもう少し大人の態度で接したらどう?」といいます。
親として子供が言うことを聞かないと嘆くことが我が家の場合少なくありませんが、子供と言うのはそもそも親の言うことなんか聞かない存在ではないでしょうか?

今朝午前6時の北グラウンド
子供はやはり親の関心を引きたいので、親の言うことを素直に聞かないのは、もう本能でプログラムされた思考回路なのだと思います。
親の言うことを素直に聞いていたら、親の関心が弾けない、親にかまってもらえない、だから本能的に親の言うことの反対をやって、怒られることによって自分の存在を確認したり、アピールしたりすると言う側面もあるのではないでしょうか?
子供が幼くて小さいうちは、子供も素直に親のいうことを聞いて親子関係も円滑にだったのに、子供の自我が大きくなってくると、子供も無意識のうちに自分の存在を忘れられたくない、もっと親にかまって欲しい、関心を持ってほしいといった本能が働くのではないかと思います。
また、親の方も子どもにもっと関わりたくて、子どもがやらないであろう要求を求めたりする傾向もあるし、やったらやったでさらにその上の要求を求めるので、結果的に子どもが親の求めるレベルに応えないという印象にもなります。
だから、むしろ子供が素直に親の言うことばかり聞いている方が私には少し違和感があり、素直に親の行くことを聞く子どもがいたとしたら、逆に何か親子関係や親子の距離感に問題が秘められているのではないか、と推測してしまいます。(それは若干偏見かもしれませんけど ^^;)

今朝の志茂町公園入口
ただし、家族の数だけ親子関係のスタイルは違っていて、みんなそれぞれ正解があるわけではないので、「こうあるべきだ」「こうでなければいけない」というものもありません。
だから、上で書いた話も我が家の中に限っての話であると思いますし、他の家には他の家の親子関係のスタイルがあると思います。
ただ、うちは時折母親としてのうちの奥さんが、子供の目線まで下りてしまって、子供が言うことを聞かないと感情的になり、またそれに煽られるように娘も感情的になってしまい、母親の方がむしろ子供のことを感情的にさせるように売り言葉に買い言葉の欧州となってしまうことがあるように見えます。
私は、大人になっていくというのは、出来る限り自分の感情をコントロールできるようになっていくことだと思いますし、特に人と話をするときは、感情的にならないように努めることが大切だと思います。
元々親の言うことを素直に聞くはずのない子どもとの会話に、親が感情的になり、また子供の感情を煽るような接し方をしてしまうと、お互いに『自分が感情的になっているのは相手のせいだ』と主張しあって、声が大きくなり、物を投げたり、物に感情をぶつけあったり、余計に相手を感情的にさせようすると自分の感情が高まってしまいます。

今朝の志茂町公園
私は、そんな時は親の方が先に子供との距離を上手に図り、時間や距離を少し開けて落ち着いてから問題の要点は何だったかを冷静に表すことができれば、もう少し建設的な話ができるとではないかなぁと思ったりします。
ただ、やはり先ほど上で書いたように、親子関係や家族関係、家庭の在り方と言うのは正解があるわけではないので、親子の数だけ親子の関係性と言う個性があっても良いものだという思いもあります。
さあ、できればお互いに昨日の出来事は頭から消して、気持ちよく新しい1日を迎えて、仲良く話が出来るように父親として上手に仲裁してあげたいと思います!
まさにこんな日の繰り返しが、平凡な日々の幸せなんですよね。